桜の季節に混む美術館。満開になる直前に楽しみにしていた展覧会を見に行くことができました。
松本竣介
松本竣介は昭和前半に活動していた画家です。
表面的にはアメリカの画家 ベン・シャーンの絵とちょっと似ていると思います。
あんなにオシャレじゃないけれど。
10年近く前、夏のおわりに岩手県立美術館にゆきました。
岩手県にゆかりの作家として展示されていた松本竣介の絵が印象に残りました。
「立てる像」は有名なので知っていましたが、その他もろもろを見たのははじめてでした。
まあ、静かで哀しい。(個人の感想です)
雨が降っていて肌寒く、立派なハコモノ・県立美術館は閑散としてどの展示室にいってもわたししかいなかったのでそういう印象を持ったのかもしれません。
松本竣介は明治45年生まれ、昭和23年にたったの36歳で亡くなってました。
中学に入学するころ、病気で耳が聞こえなくなっていたそうです。
子ども時代からぎっしり持っておられた様々な思いが絵に表れていたのかな、と想像。
松本竣介 街と人 冴えた視線で描く
展覧会のメインは都会の風景画です(たぶん)。
デッサンとタブローがセットで展示されているものもあり、制作過程を想像することができます。
きれいな色+味わい深い線画の複雑な絵もいいけど、暗い色で描いた都会の風景がとくによいのです。
たぶんほんとは静かじゃないのであろう駅とか工場とか橋が静かに描かれています。
デッサンは駄菓子屋の袋みたいなテクスチャのハトロン紙やざら半紙に描かれているのがすてき。
いちばん印象的だったのは横浜の月見橋を描いた「Y市の橋」でした。
静かで哀しい、いい風景画。
展示されていた絵以外にも何点か同じ月見橋の風景画があって、全部いいんです。
あのごちゃごちゃした横浜駅の東側が昔はこんなだったというのも興味深い。
風景だけではなく、子どもや奥さんをモデルにした絵もあります。
かわいくてたまらないのであろう子どものやわらかそうなあったかい絵。
それでもやっぱりなんだか哀しく感じるのですが。
絵によっていろんなタイプのサインがはいっているのがおもしろい。
漢字だったりローマ字だったり、イニシャルを組み合わせた野球チームのマークみたいなのもありました。
地中館に松本竣介が影響を受けたというモディリアニ、ルオーの絵が展示されていました。
見るからに「影響うけてるよな」っていう絵もあるはずなんだけど展示されていなかったので、それもみたかったなぁ。
もっと大きな美術館でいろいろ見たい松本竣介の作品でございました。

アサヒグループ大山崎山荘美術館
アサヒグループ大山崎山荘美術館は、JR山崎駅から「あかずの踏切」を渡って10分ぐらい山登りしてたどり着く美術館です。
いつもはJR山崎駅か阪急大山崎駅から歩いてゆきます。
この日は昔住んでいた団地(大山崎に住んでいました)から美術館まで歩いてみました。
竹藪だらけの暗くて怖い道だったところは家がいっぱい建って明るい道になっていました。
こんなところにまで家が建つのかってぐらい建ってるじゃないか。
子どもの頃は山の中の廃屋だと認識していた山崎山荘は今や立派な美術館になりました。
まさか将来この廃屋の中に入る日が来るとは想像もしませんでした。

美術館のテラスからは桂川、宇治川、木津川が合流して淀川になる「三川合流の地」であることがよくわかる景色が見えます。
宇治川と木津川を分ける背割堤に桜並木があり、満開になるとテラスからの風景はぐっと華やかになります。
その時期美術館が混むので、それまでに松本竣介展に行かなければ!と思っていました。
背割りの桜が満開になるのは来週ぐらいかなぁ…って感じでした。

大山崎山荘美術館あり、聴竹居あり、サントリーウイスキー工場あり…
たまに行くだけなら大山崎はいいところです。
田畑がなくなり住宅が増えて町の姿はすっかりかわりましたが、JR山崎駅横のあかずの踏切は相変わらずなかなか開かないのでした。
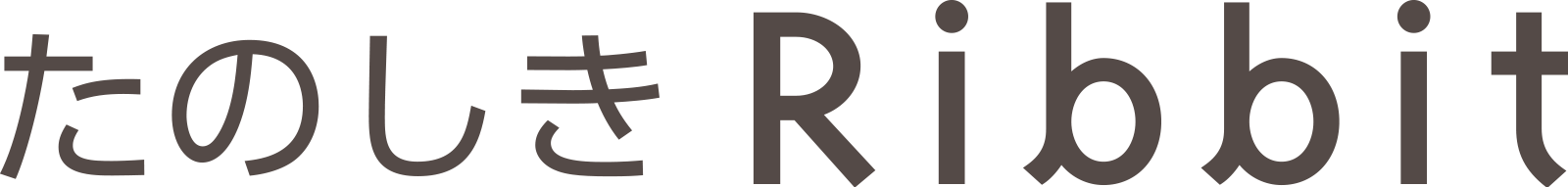


コメント